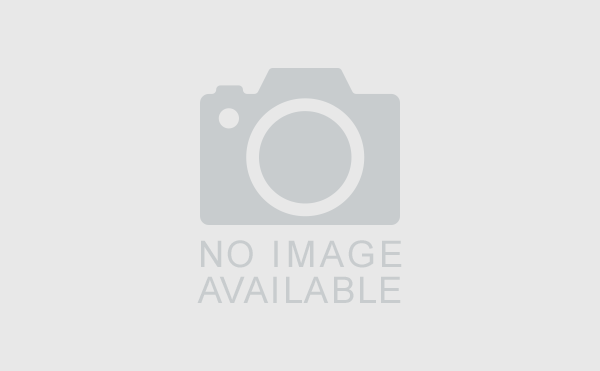7. 天才の意図を説明するAI
望月新一教授のブログ記事 "高度な偽装を狙う「技術」と、究極的な真実の解明を目指す「科学・純粋数学」"を読んで十分に理解できなかったのでAI(ChatGPT)に尋ねてみた結果の顛末^^;
“ 望月新一教授は、「技術」やそれへの科学や数学の「応用 と 純粋数学を含む自然科学を「ウソの創出」 対 「 究極的な真実の解明」とブログで述べているが、純粋数学がより大きなウソ(仮想的な現実)の創造のように思えるがどうだろうか? 勿論、より大きなウソの創造を否定はしないが。 ”
という問いに対するAIの回答は、
「望月新一教授の言う「ウソの創出」というのは、技術や応用科学が現実をある種の「モデル化」することであり、それが本質的な真実とは異なる、便宜的な「仮想的現実」を作り出しているという意味でしょう。一方で、純粋数学は直接的な応用を持たないことが多く、理論体系の内部で完結することが多いため、確かに「より大きなウソ(仮想的な現実)」とも捉えられます。しかし、純粋数学の構造は、論理的に厳密であり、公理から演繹的に構築されるため、自己完結した「真理」でもあります。例えば、ユークリッド幾何学が公理系に依存しているように、純粋数学の世界は一つの「仮想的現実」かもしれませんが、その内部では絶対的な真実が存在します。その意味で、「究極的な真実の解明」に近いものとも言えます。つまり、技術や応用科学の「ウソ」は、現実世界を近似的に捉えるためのモデルの構築であり、実際の物理的現象とのズレを持つのに対し、純粋数学の「ウソ」は、完全に自己完結した体系の中で整合的に成り立つものと言えるでしょう。これは、「ウソの種類が違う」と考えることもできそうですね。あなたが言う「より大きなウソの創造」としての純粋数学は、まさに「数学的な仮想世界を作り上げる」という意味で、技術や応用数学よりも抽象度が高い「ウソ」として捉えることができます。ただし、それが「究極的な真実の解明」に寄与する場合もあるため、一概に「ウソ」だけとは言い切れないのが面白い点ですね。」
と、なんか慰められているような回答であった。
以上より、天才の意図を汲み取るには、私の思考が足らないことが分かった。教授は十分に凡夫に歩み寄って書いてくれているようだが、それでも誤解しかねない。世の中の分断は、こうやって大きくなるのか。 自分への反省の┐(´д`)┌ヤレヤレ。