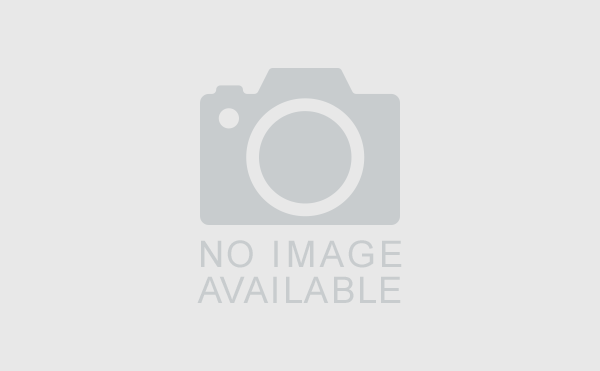13. 川中不動(国東半島)
先に訪れた9. 真木大堂(国東半島)に続いて、国東半島の寺社参りをした。今回は、国東半島のほぼ中央の山間に位置する文殊仙寺を目指して車を走らせた。宇佐方面から豊後高田市街を抜けて県道548号を登っていくと、天念寺の案内看板が屡々目に入る。本来、私は目的地に計画的に向けて動き、寄り道が嫌いな性格であるが、前回の真木大堂の時と同様に何とは無く惹かれて、脇道へと入った。
天念寺は養老2年(718年)、六郷満山(国東半島一帯にある寺院群の総称)を開いたと伝えられる仁聞菩薩によって創建されたとされる古刹である。平安から鎌倉時代にかけては修験と祈願の寺院として栄え、六郷満山の中山本寺として重要な役割を果たしてきた。現在では住職もおらず、少し荒れた印象も受ける小さな寺だが、地元では信仰の厚い霊地として今も大切にされている。特に有名なのが、毎年旧暦正月に行われる「修正鬼会(しゅじょうおにえ)」という伝統行事である。この祭りの様子を天念寺の近くにある鬼会の里 歴史資料館の映像で見たが、YouTubeでも公開されている。なかなか激しい祭りで、赤い災払鬼と黒い荒鬼は、先祖の霊ともされており、松明に仏の法力をこめて火の粉を浴びせながら参拝者の背中などを叩き、福(家内安全・五穀豊穣・無病息災など)を届ける。
川中不動(かわなかふどう)は、天念寺前を流れる長岩屋川の中にある巨岩に彫られた不動明王の磨崖仏である。この仏像は室町時代に彫られたとされ、かつて暴れ川であった長岩屋川の水害除けとして刻まれたと伝えられている。川中不動は、高さ約3.7メートルの不動明王像で、両脇に1.7メートルのコンガラ童子とセイタカ童子を従えている。この三尊像は、川の中の大岩に直接彫られており、正面に設置された祭壇から間近に拝むことができ、迫力ある姿である。
国東半島の仏教文化は、奈良時代に始まり、山岳信仰・修験道・天台宗が融合して形成された、非常に独自性の高い宗教文化圏である。天台宗、真言宗の影響が色濃く、六郷満山を構成する多くの寺院で不動尊が見受けられる。不動明王は、自分の守護本尊なので余計に目につくのかも知れないが。